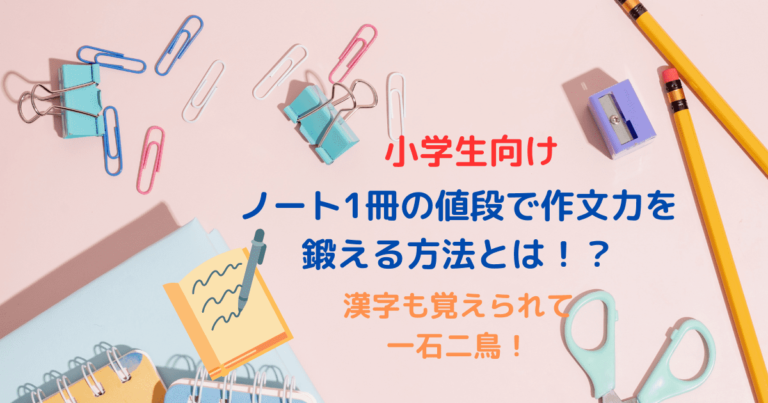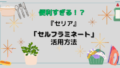作文力を鍛えるために、お手軽にできる方法はないかですか?

ありますよ!
この記事では、ノート1冊で作文力と、おまけに漢字も覚えられる方法を紹介します。
その方法は、日記を書くことです!
夏休みなどの、長期休暇を利用して始めるのがおすすめです。
実際に、私の子供たちもこの方法で、少しずつですが、作文力が身についてきました。
どんな方法か、気になるかたは記事の続きをご覧ください。
作文力をノートの値段で鍛える方法
ノート1冊の値段で、作文力を鍛える方法は「日記」です。
日記での作文力を鍛える方法は、子供達の学校でも推奨されており、先生も「日記」での作文力向上については、よくお話をされています。
4つのルールを守ることで、日記を書くことで作文力を鍛えることができます。
- 最低、3文書く。
- 原稿用紙の使い方のルールを守る。
- 習った漢字は必ず使用する。
- 必ず、大人が目を通して添削をする
では、なぜこの4つのルールで作文力を鍛えることができるのか説明をしていきます。
最低、3文書く
なぜ、3文なのかというと、3文で「はじめ、なか、おわり」を意識することができるからです。
1文ですと「今日は楽しかった。」だけで終わってしまい、何が楽しかったのかわかりません。
2文でも「今日は、遊園地に行った。とても楽しかった。」となり、遊園地に行って楽しかったということしか伝わりません。
それが、3文になると「今日は、遊園地に行った。そこで、お父さんとジェットコースターに乗った。とても楽しかった。」となり、遊園地の何が楽しかったのかまで伝わるようになります。
作文の構成の基本となる「はじめ、なか、おわり」を意識をすることがてぎるので、日記は最低3文書くことが望ましいのです。
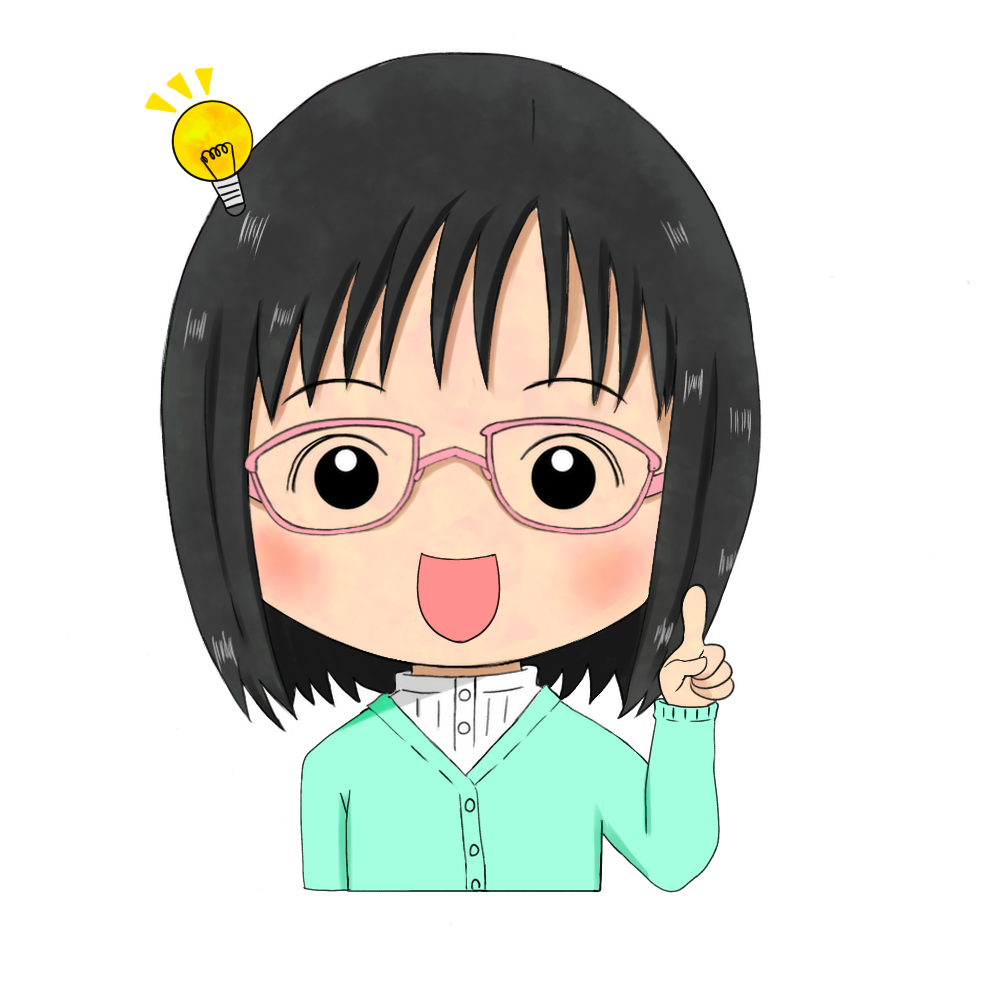
「はじめ・なか・おわり」は作文にとって重要です。
書くときは原稿用紙の使い方のルールを守る
こちらは、そのままのです。日記とはいえ、原稿用紙の使い方を意識することで、原稿用紙の使い方のルールを覚えていくことができます。
そのために、日記を書くノートは原稿用紙スタイルのものがオススメです。
低学年のお子さんには、マスが大きいものを選んであげてください。
書き出しは、一マス空けるなどの基本的なルールは、日記でも使用頻度が高いですが、よく間違えるポイントでもあります。
普段から、そういった基本的なルールを実際に使用することで、作文を書くときに困りまりにくくなるはずです。
習った漢字は必ず使用する
これが、一石二鳥のポイントです。
漢字は、使わなと忘れていきます。
あなた自身も、スマホに慣れすぎて、咄嗟に漢字が書けないことはありませんか?
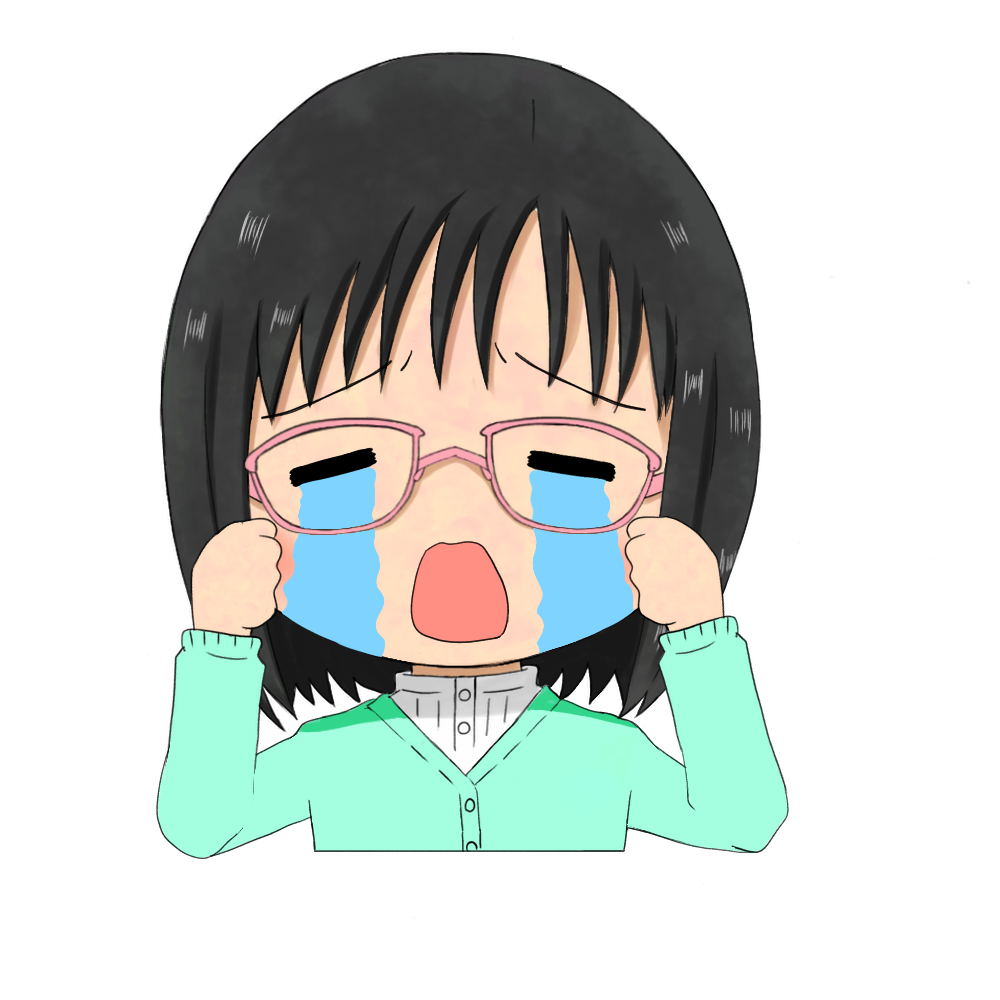
私はよくあります。
ですので、習った漢字は、意識をして使ったほうがいいのです。
でも、漢字練習は大変。
そこで、役に立つものが「日記」です。
作文の練習と漢字を使う習慣を、1回で合わせてできるので、効率がいいですよね?
実際に、この方法で私の子供たちは、日記を始める以前よりも、漢字が書けるようになりました。
必ず、大人が目を通して添削をする
これは、間違いをすぐに訂正するために重要です。
添削ポイントは少なく「上記のルール3つを守っているか」だけです。
せっかくのルールですが、守られていなければ何のためにもなりません。
ですので、書き終わったら、日記を見せてもらい添削をしてあげてください。
もし、原稿用紙の使い方に不安を感じるかたは、こちらの本がおすすめです。
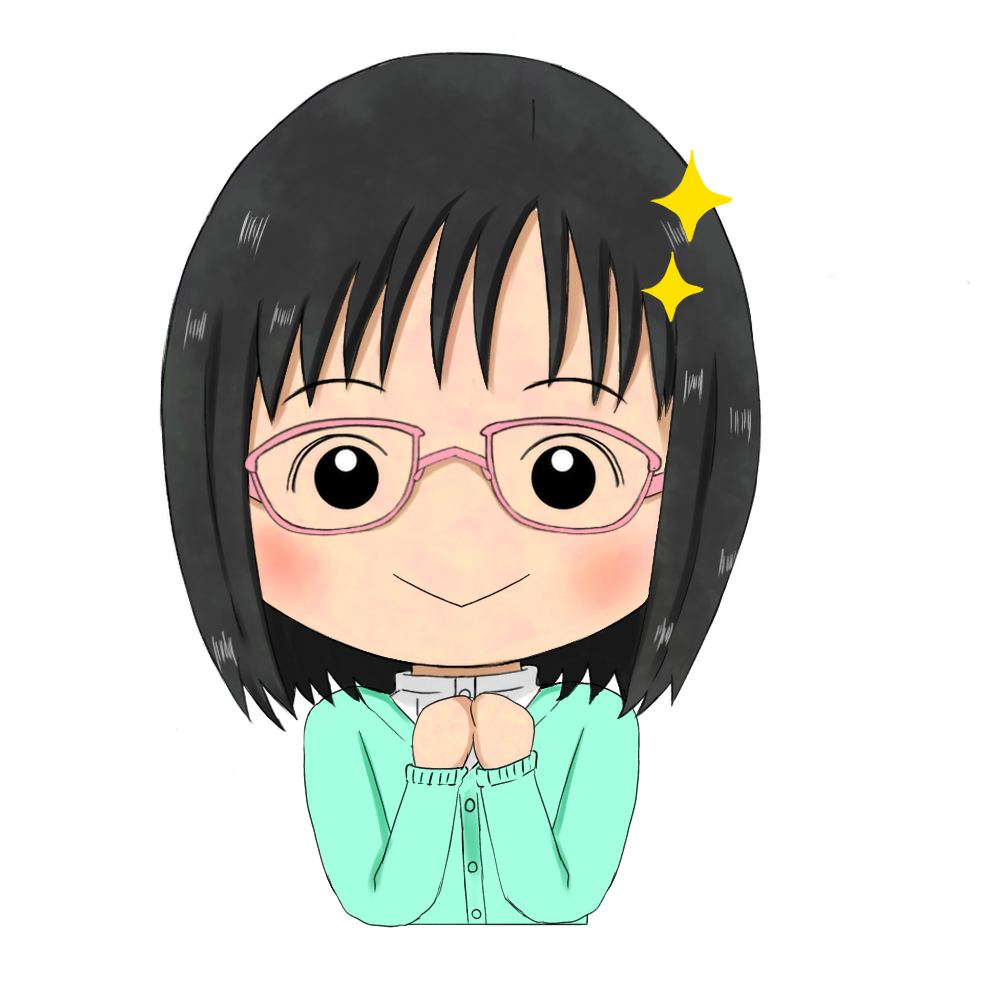
中学生向きですが、とても分かりやすく書かれていました。
日記でおすすめのテーマ
高学年になると、「日記」を親に見せたがる子は少ないはずです。
そこで、普通の「日記」ではなく、テーマを出してそれについて、書いてもらうことをおすすめします。
おすすめのテーマは下記の通りです。
- ペットの観察日記
- 漫画を含めた読んだ本の感想
- 芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと
- 気になった新聞記事について

日記に見えないものもあるけど、どうして?
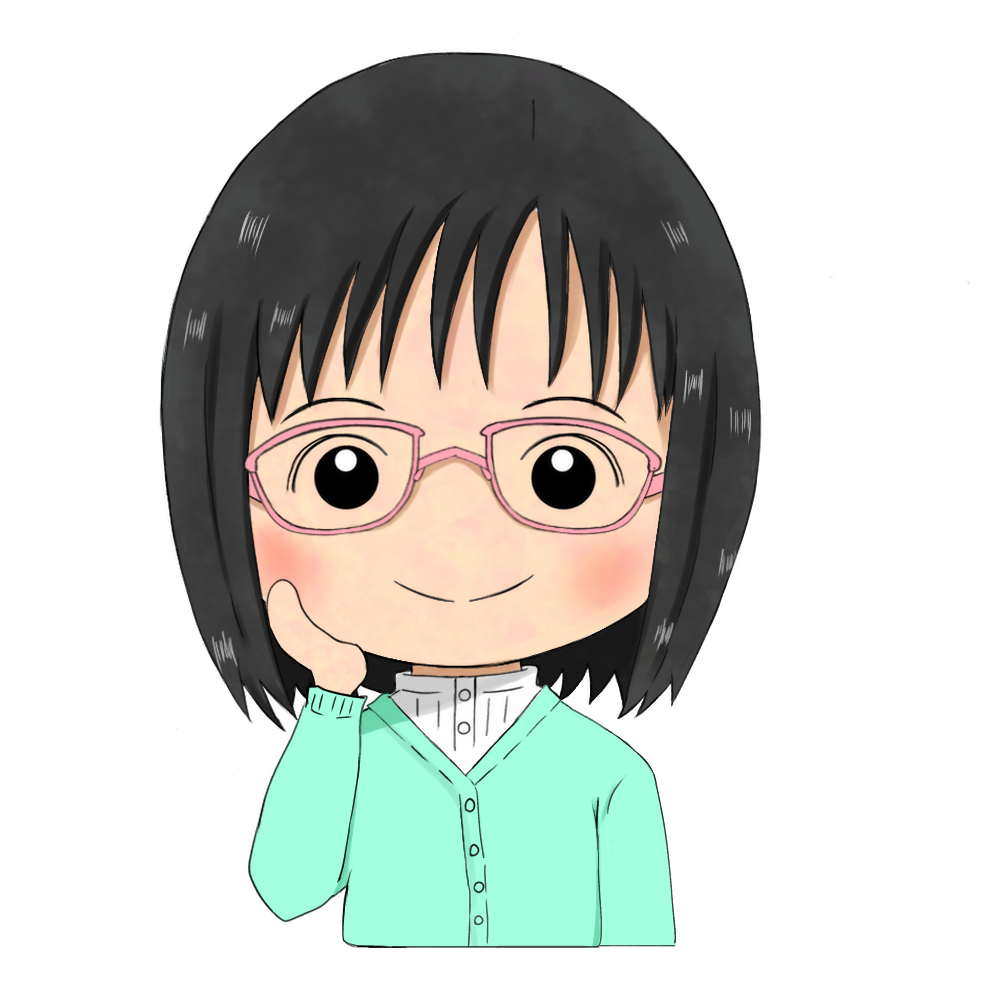
それは、中学生以降のためです。
ペットの観察日記
ペットの観察日記は、まさにそのままですのです。
ペットととの日常を、イラスト付きの絵日記にしても、面白いかもしれませんね。
漫画を含めた読んだ本の感想
読んだ本の感想もそのままですが、これは読書感想文の練習をしたいわけではないので、とにかく書いてもらうことが重要になります。
ですので、漫画でもいいので、読んでどんなところが面白っかた、このキャラクターのこんなところが好きなどといった、軽い感じで書いてもらと、続けやすくなります。
芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと・気になった新聞記事について
では、最後にまとめて「ニュース」と「新聞記事」の理由を説明します。
この2つは、いずれ書くことになる小論文を意識しています。
私の出身県では、高校受験の推薦枠で小論文・一般入試で作文があります。
小論文・作文対策として、私が中学生時代に、家庭教師の先生から勧められたのが「ニュース」「新聞記事」の気になったものを選び、それに対する自分の考えと世の中の考えをまとめることでした。
理由としては、「小論文は慣れと情報がなければ書けない」とのことです。
ですが、これは中学生の話です。
小学生には難しいので、芸能ニュースや流行していること、興味の持てたものについて、なぜ興味があるのかや感想を書いてもらうのがいいと思います。
ニュース・新聞を見る習慣がつくので、中学生以降の社会科の時事問題にも強くなれるはずです。
子供向けの新聞もあります。子供向けの新聞が気になる方は、朝日小学生新聞は中学受験に最適?デジタル版も?料金は?お試しは?休刊日は?お試しをしてみました!をご覧ください。
日記の三日坊主対策
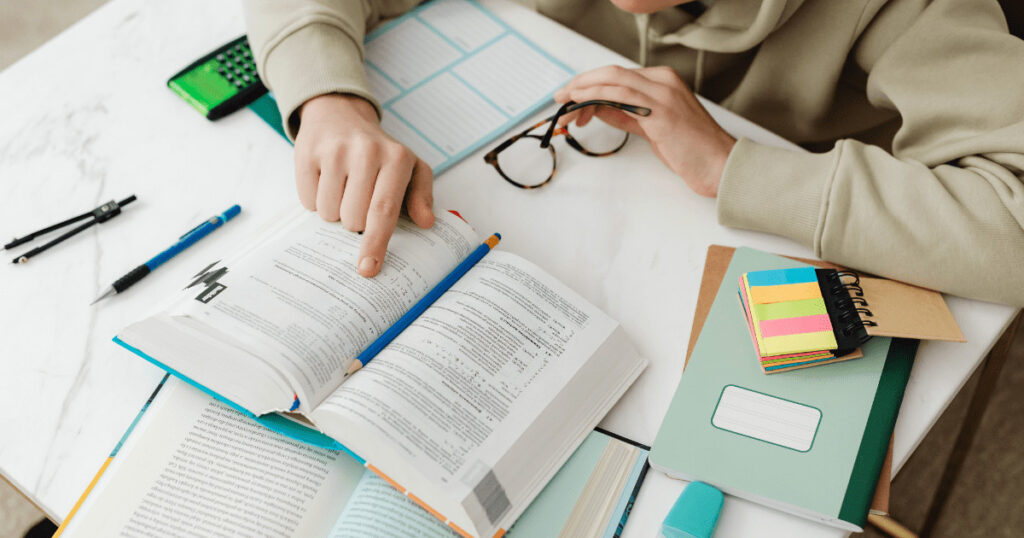
「日記」において、三日坊主は天敵です。
私自身もですが、子供たちもなかなか続かず大変でした。
そこで、私が取った対策は、期間を決めるです。
例えば、金土日だけ書くや長期休暇中のみ書くようにするです。
思いのほか、期間をくぎることで終わりが見えるためか、その期間は真面目に取り組んでくれました。
合わせて使いたい作文力ドリル
日記だけでは不安なあなたには、一緒に使用して効果を高めるための、作文力ドリルを2つ紹介します。
『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』
かんき出版から発行されている『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』。
こちらは、監修者である、安藤英明さんが、作文が苦手な子供たちの声を、参考にして作られたドリルです。
このドリルの特徴は、
- 学年を問わず使える
- ゲーム感覚で語彙力を鍛えられる
- 接続詞に強くなる
- ダウンロード特典で繰り返し学習できる になります。
実際に、使用した感想は「楽しく学べるドリル」だなと思いました。
特徴にもあるように、ゲーム感覚で語彙力を伸ばせるので、兄弟で競い合いながら取り組むことができました。
使用した当時1年生だった下の子も、すべての漢字にふりがながついているので、無理なく取り組むことができたようです。
ただ、言葉が思いつかなっかたときのために、国語辞典は用意しておいたほうがいいです。

辞書で言葉を探すのは、早い者勝ち感があって面白かったよ!
大人も、意外と思いつかな文字数の言葉があるので、親子で一緒に取り組むことがですます。
『作文力ドリル』シリーズ
学研プラスから発行されている、『作文力ドリル』シリーズ。
そのシリーズ『作文の基本編 小学低学年用』を紹介します。
このドリル特徴は、
- ストーリーを進めながらの学習
- イラストから自分で考えて書く
- 文章を4段階に分ける構成で書きやすく になります。
実際に、使用した感想は、「イラストのストーリーを読みながら、文を書き進めるのでストーリーを楽しみながら学習することができるな」です。
しかし、1つ前に紹介したものと違い、いきなり文を書いていくので、1年生には難しいように感じました。
ですので、まず先に『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』を使用してから、『作文力ドリル 作文の基本編 小学低学年用』を使用することをおすすめします。
『小学1年生から論理的に書ける「三文作文」練習帳』
日記なんて無理!とういお子さん向けの練習帳です。
小1レベルから徐々に上がっていくので、低学年からも取り組みやすくなっています。
レベルが上がるごとに、三文から四文といった具合に、文の数も増えますが、この文ではこんなことを書いてといった内容が書いてあるので、無理なく進めることができます。
イラストを見て文を書く問題は、同じイラストがレベルが上がるごとに毎回出てくるので、どんどん文が詳しく書けていることが自信に繋がるはずです。
作文が苦手な上の子が、これが一番継続できています。
まとめ
作文力をノートと1冊の値段で、漢字もあわせて覚えられる方法は「日記」です。
必ず、日記は添削をしてください。
普通の日記を見せたくないお子さん向けのテーマは、
- ペットの観察日記
- 漫画を含めた読んだ本の感想
- 芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと
- 気になった新聞記事について です。
三日坊主対策におすすめの方法は、期限を決めて終わりを設けることです。
日記だけでは、不安かたにおすすめのドリルは、
- 『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』
- 『作文力ドリル』シリーズ です。
ぜひ、4つのルールを守りながら、日記での作文力向上に取り組んでみてください。